ストレスによるメンタルヘルス不調は、心身にさまざまな影響を及ぼします。イライラや不安、気分の落ち込み、休息しても疲労が取れないなどの状態が続いているのなら、その背景にはメンタルヘルス不調がある可能性もあります。メンタルヘルスの安定は、いきいきとした毎日につながるものです。そこで注目したいの が 、メンタルヘルスの強化や安定に関わる「レジリエンス」の向上です。自分自身のレジリエンスを高めることで、メンタルヘルス不調を防げるようになります。本記事では、レジリエンスとは何か、具体的にどのようにしてレジリエンスを高めればよいのか、またレジリエンスが高い人の特徴などについて解説します。(以下、専門家監修による記事です)
目次
1.「レジリエンス」とは?
レジリエンスとは、日本語で「回復力」や「弾力性」などと訳される言葉です。心理学的には、困難や逆境などのストレスを受けた際に「精神的に回復するプロセス」を意味します。回復という現象そのものや、回復に寄与する心理的な状態を指す場合もあります。
社会環境が目まぐるしく変化している近年、働く人々のこころのケアにも高い注目が集められており、レジリエンスの向上もその1つです。レジリエンスを高めることで、変化に抵抗せず受け入れる適応力や、逆境や困難に直面しても元の状態に戻ろうとする回復力が向上します。
レジリエンスが向上すると、ネガティブな出来事によって生じるストレスを緩和するだけでなく、災難を内的な成長にもつなげられます。レジリエンスの向上によって、メンタルヘルス不調を起こしづらくなることに加え、人間的な成長も期待できるのです。
2.レジリエンスが高い人にある3つの特徴
レジリエンスが高い人には、行動や物事の考え方、周囲との関わり方にも特徴がみられます。ここからは、レジリエンスが高い人に見られる3つの特徴についてみていきましょう。
問題をポジティブにとらえられる
レジリエンスが高い人は、困難や逆境に直面しても、「これは失敗ではなく経験だ」と捉える柔軟な思考を持っています。たとえば、仕事でミスをしてしまったときも、ただ自分を責めるのではなく、「なぜこうなったのか」「次に活かせることは何か」と建設的に考える姿勢が特徴的です。
このような前向きな姿勢は、「リフレーミング」と呼ばれる心理的スキルによって支えられています。リフレーミングとは、物事の見方を意識的に変え、ネガティブな出来事の中にも意味や価値を見出す方法です。レジリエンスの高い人は、このスキルを日常的に使いながら、ストレス状況を成長の機会として捉える力を養っています。
感情をコントロールできる
レジリエンスが高い人は、自分の感情に巻き込まれることなく、冷静に判断できるという特徴があります。不安や怒り、焦りなどのネガティブな感情が湧き起こったときにも、それを否定したり我慢したりするのではなく、「今、自分はこう感じている」と一歩引いて観察する力を持っています。自分の感情を冷静に捉えることで、感情的な反応ではなく、自分の意思に基づいた行動を選べるようになります。
このように、自分の思考や感情、行動を客観的にとらえ、認知・評価・調整する能力のことを「メタ認知」といいます。この能力があると、感情に振り回されず、落ち着いた判断や行動がしやすくなります。結果として、周囲との関係性や課題への対処もうまくいきやすくなり、自信や安定感にもつながるのです。
周囲と協力的な関係を築ける
レジリエンスは、個人の精神的な強さだけでなく、他者との関係性の中で育まれる側面も持ち合わせています。困難な状況に置かれた際に、自ら周囲に支援を求めたり、信頼関係を構築したりする力は、レジリエンスの重要な構成要素とされています。
レジリエンスの高い人は、日常的に周囲とのつながりを意識し、感謝や共感の姿勢をもってコミュニケーションをとる傾向があります。また、単に支援を受ける立場にとどまらず、自身も、周囲の人たちにとって安心感を与える存在となるような関係性を築いていきます。
このような相互的な支援関係は、社会的孤立を防ぎ、ストレスを緩和してくれるものです。「支え合える関係がある」という実感そのものが、レジリエンスを高める土台となるでしょう。
3.レジリエンスを高めるための2つのポイント
レジリエンスは、生まれ持った資質だけで決まるものではありません。誰の中にも備わっている力であり、環境や経験、日々の習慣によって伸ばしていくことが可能です。実際、同じような困難に直面しても、その受け止め方や回復力には個人差が見られるものです。
この違いは、性格や思考のクセ、育ってきた環境、人との関係性など、さまざまな要因によって変わるものです。そして、意識的な取り組みによってレジリエンスを強化できます。
ここからは、日常生活の中で取り入れやすく実践的な、変化につながりやすい「2つのポイント」に絞って、レジリエンスを高めるためのヒントをご紹介します。
問題を積極的に解決しようとする意志
レジリエンスを高めるうえで重要なのが、問題から目を背けず、向き合おうとする姿勢です。困難に直面したときに、その状況をただ嘆くのではなく、「自分にできることは何か」「どうすれば乗り越えられるか」と考え、前向きに行動を起こすことが大切です。
このような「問題を積極的に解決しようとする意志を持ち、解決方法を学ぼうとする力」は、特別な能力ではなく、日々の姿勢の積み重ねによって身につけられます。たとえば、仕事においては、与えられた指示を待つのではなく、自ら課題を見つけて取り組もうとする意識を持つことが、主体性や応用力を高める第一歩になります。また、業務上のトラブルに直面した際も、「どうしたら解決に近づくか」という視点で動くことで、状況を打開する力が培われていきます。
プライベートでも、日常の小さな課題に対してさまざまな角度から解決策を考え、実行に移すよう習慣づけていきましょう。さらに、新しいことに挑戦することも重要です。チャレンジの中で生じる課題を自分の力で乗り越える経験の積み重ねが、柔軟で折れにくいこころをつくる基盤になります。
自分を理解することと他者の心理を理解すること
レジリエンスを育てるうえで欠かせないのが、「自己理解」と「他者理解」の両立です。自己理解とは、自分の感情や思考の傾向、行動パターンを把握し、それに合った行動や目標を選択できる力のことです。一方、他者理解とは、相手の立場や感情、背景を推測し、尊重しながら関わる力を指します。
自己理解を深めるために、自分の感情や反応を客観的に見つめることを習慣づけましょう。そのための方法として、日報や日記を通じて1日の出来事や自分の気持ちを振り返る「内省」の時間を持つことが有効です。忙しい日々の中でも、「なぜ自分はあのとき不快に感じたのか」「本当はどうしたかったのか」と問いかけることで、自己認識が深まります。
一方で、他者の心理を理解する力もレジリエンスを支える重要な要素です。ここでいう他者理解は、単なる共感とは異なり、「相手はなぜそのように感じたのか」「どんな価値観や経験が背景にあるのか」といった、相手の視点や論理を考える姿勢を含みます。これは、対人関係での摩擦や誤解を減らし、柔軟な対応力を高めるベースとなります。
さらに、自己理解・他者理解の両方を深めるためには、継続的な学びも大切です。心理学、コミュニケーション、文化、社会的背景など、さまざまな知識を取り入れることで、より多くの視点を持つことができ、自己や他者に対する理解の枠組みを学ぶことにもつながります。
4.メンタルヘルスの安定のために取り組みたい「セルフケア」
レジリエンスの向上は、ストレスへの対処力や回復力を高めるうえで重要な要素ですが、それだけでは十分とは言えません。日々の中で蓄積する心身の疲労やストレスを、自分自身でケアする「セルフケア」もまた、メンタルヘルスを安定させるうえで大切な習慣です。
セルフケアとは、自分のこころと身体の状態に気づき、適切に整えるための具体的な行動のことです。自分自身を整えることで、ストレスの悪化や慢性化を防ぎ、より健やかな日常を取り戻しやすくなります。
ここでは、精神的な安定を保つために、日常生活で無理なく実践できるセルフケアの方法をご紹介します。
自分のこころと身体に耳を傾ける
セルフケアの第一歩は、自分自身のこころと身体の状態に気づくことから始まります。どれほど忙しく日々を過ごしていても、自分の変化に目を向ける意識がなければ、不調のサインを見逃してしまうかもしれません。
以下のような状態が続いている場合、ストレスやメンタルヘルス不調が背景にある可能性があります。
- 強い疲労感がある
- ゆううつな気分が続く
- 倦怠感が抜けない
- 不安を感じることが増えた
- 気分がなかなか晴れない など
こうしたサインを見逃さず、早めに気づくためには、日常的に自分のこころと身体の声に耳を傾ける習慣が役立ちます。その1つの方法として、日記やメモに今の気持ちを書き出すというシンプルな取り組みが効果的です。
頭の中にある感情や思考を言語化することで、ストレスや悩みの正体が見えてきます。また、気持ちを書き出すことは、自分を客観視するきっかけにもなります。「最近、疲れていると感じることが多い」「同じようなことでイライラしている」など、自分の傾向やリズムを把握する手助けにもなるでしょう。
こころと身体のささやかな変化に気づき、変化が小さなうちから対処することが、メンタルの安定を保つためのセルフケアの基本です。
心身の緊張をやわらげる習慣を持つ
セルフケアは、特別なスキルや時間が必要なものではありません。日常の中で無理なく取り入れられる、小さな行動の積み重ねが、こころと身体の健やかさを保つカギとなります。とくに大切なのは、心身の緊張をやわらげる習慣を持つことです。
たとえば、数分間のストレッチや深呼吸、軽いヨガなどは、緊張状態にある身体をほぐし、自律神経のバランスを整えるのに効果的です。難しいポーズをとる必要はなく、椅子に座ったままできるような簡単なストレッチでも十分です。オフィスや自宅など、場所を選ばず手軽に取り組めます。
また、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動も、ストレスの軽減や気分のリフレッシュに役立ちます。無理に続けようとせず、自分が「楽しい」と感じる運動を選ぶことが継続のポイントです。週に数回、短時間でも身体を動かすことで、心身のバランスを保ちやすくなります。
質の良い睡眠も重要です。ただ長く眠るのではなく、朝すっきり目覚められる、日中に眠気が続かない快適な睡眠を意識しましょう。仕事中に15分程度の短時間の昼寝を取り入れるのも、心身のリセットに効果的です。
そして、人とのつながりも意識しましょう。気の置けない友人とのおしゃべりや、こころから笑える時間は、こころの緊張をやさしくほどいてくれます。こうした時間こそが、日常のストレスを乗り越えるためのこころの栄養になるのです。
5.困難に負けないこころと身体をつくろう
日々の生活の中で、ストレスや困難を避けることはできません。しかし、自分のこころと身体に向き合い、レジリエンスを育み、セルフケアを実践することで、それらに押しつぶされない「しなやかな強さ」を身につけられるでしょう。
本記事で紹介した取り組みは、一度きりで完結するものではなく、日常の中で繰り返し意識し積み重ねていくことが大切です。不安やストレスの多い現代社会だからこそ、レジリエンスの向上を目指して、できることから少しずつ取り組んでみましょう。
<編集部より>
つらい状況やネガティブな状況を解消できない場合は専門家に頼ることも1つの手段です。「誰かに悩みを聴いてもらいたい…」そんなときに利用できる『心理カウンセリング』をご存じですか?詳しくはこちらをご覧ください。

<<監修者プロフィール>>
小塩真司(おしお・あつし)
心理学者・早稲田大学文学学術院教授
1972年愛知県生まれ。名古屋大学教育学部卒業、同大学院教育学研究科教育心理学専攻修了。博士(教育心理学)。中部大学准教授などを経て、早稲田大学文学学術院教授。専門はパーソナリティ心理学、発達心理学。著書に『自己愛の青年心理学』(ナカニシヤ出版、2004年)、『はじめて学ぶパーソナリティ心理学』(ミネルヴァ書房、2010年)、『性格を科学する心理学のはなし』(新曜社、2011年)、『非認知能力:概念・測定と教育の可能性』(北大路書房・共著・2021年)などがある。
※当記事は、2025年8月に作成されたものです。
※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。



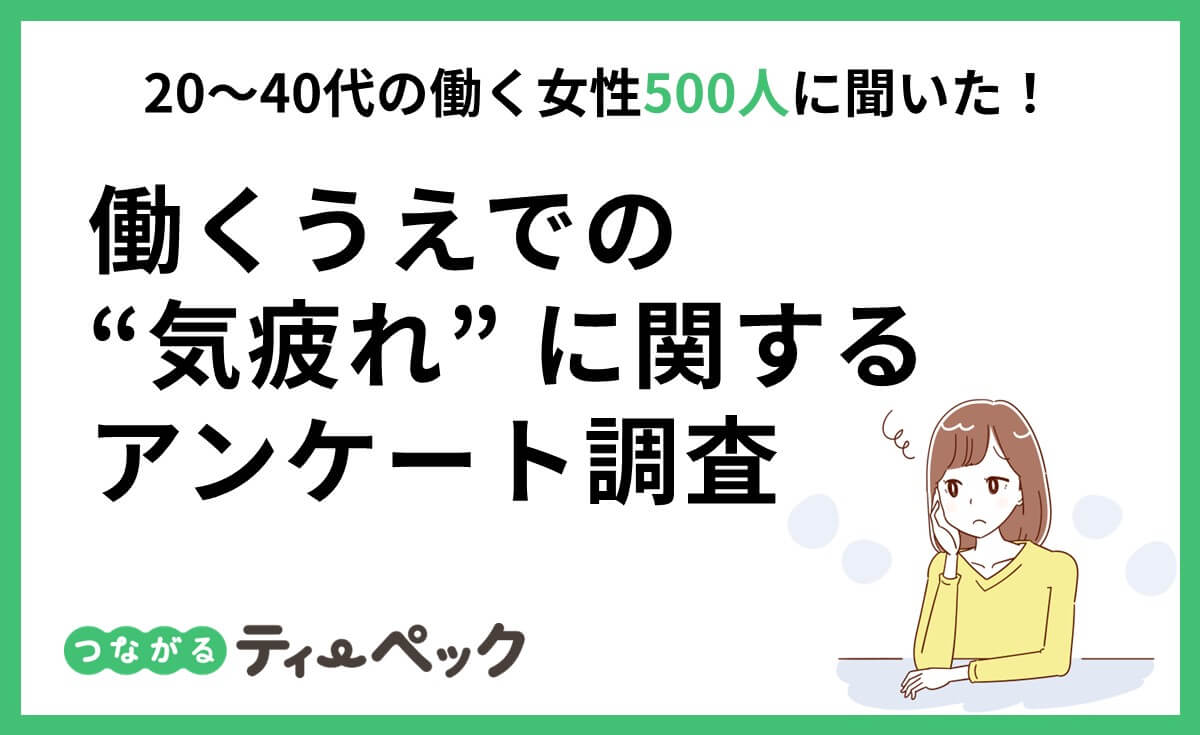


いただいたコメントはつながるティーペック事務局に送信されます。 サイトに公開はされません。 コメントには返信できませんのでご了承ください。