「必要以上に人に気を遣ってしまう。」「誰かと一緒にいると疲れる。」などとお悩みの方はいませんか?令和4年の国民生活基礎調査にて、悩みやストレスのある者(15歳以上)4598万名を調査した結果、最も気になる悩みやストレスの原因として、家族との人間関係をあげた人は265万5千名、家族以外との人間関係をあげた人は233万2千名であることがあきらかになりました。この調査結果から、約10人に1人が人間関係で深く悩んでいることが分かります。(※1) この記事では、人に気を遣い過ぎて人間関係で疲れてしまう人に向けて、気疲れの原因や対処法を紹介します。気疲れする原因を知り、適切にアプローチすれば、人間関係に悩む場面を減らすことができます。本記事を読み、人間関係を楽にするためのコツを学びましょう。
目次
1.「気疲れ」とは?
気疲れとは、一般的に「他者への過度な気遣いや緊張から精神的に疲労すること」を指します。他人の顔色を気にして自分の気持ちを押さえつけてしまうことなどが、「気疲れ」の具体例としてあげられます。
気疲れしやすい人は、人との交流を避けてしまったり、仕事で疲労感を感じやすかったりするため、生きづらさを感じるケースが多くあります。
2.気疲れしやすい人の特徴は?内面の要因
気疲れしやすい人の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、気疲れしやすい人が持つ以下3つの特徴を紹介します。
- 過度に人目を気にする
- 完璧主義
- 責任感が強い
2.1過度に人目を気にする
気疲れしやすい人の特徴1つ目は、過度に人目を気にすることです。
気疲れは、他者への過度な気遣いや緊張から、精神的に疲労することを指します。過度に人目を気にする人は、自分の意見を言えなくなったり、自分が本当にしたい行動ができなくなったりします。
他者を気にしすぎてしまうと、自身の本当の気持ちを押し殺してしまうため、人間関係で過度に疲れてしまうのです。
2.2完璧主義
完璧主義も気疲れの原因の1つです。
気疲れしやすい人は、メールを1通送るにしても、タイプミスや伝達漏れがないかなどを何度も確認してしまうケースが多々あります。このことから、少しのミスも許せない完璧主義の人は、人間関係においても疲れやすくなると考えられます。
2.3責任感が強い
業務や人間関係において気負いすぎてしまう傾向にあるため、責任感が強い人も気疲れしやすいといえるでしょう。
責任感が強い人は、頼まれた仕事を断れなかったり、自身のプライベートは後回しにして仕事を完璧にこなそうとしたりします。
真面目に業務をこなす人がいることで全体の業務がスムーズに進むなど、組織にはよい影響を与えるケースも多くあるでしょう。しかし、当人は自身のキャパシティーを超えて仕事に取り組んでしまうことも多いため、ストレスや疲労を抱えやすいのです。
3.気疲れしやすい原因は?環境の要因
もともとの性格などの内面だけでなく、環境面の問題により気疲れしやすくなっているケースもあります。
ここでは、気疲れしやすい環境の原因として以下3つを紹介します。
- 複雑な人間関係の中にいる
- 仕事量が多く残業続き
- 転職や引っ越しなどで環境に大きな変化があった
3.1複雑な人間関係の中にいる
複雑な人間関係の中にいる人は気疲れしやすくなると考えられます。
例えば、職場で部長や課長といった中間管理職を担う人は、上司と部下の板挟みになりやすいため人間関係でストレスを抱える場合が多くあります。また、お子さんがいる方であれば、ママ友との人間関係が子どもの友人関係に影響することもあるため、必要以上に気を遣ってしまい、気疲れすることもあるでしょう。
高いコミュニケーション能力が求められる環境にいる人ほど、気疲れしやすくなります。
3.2仕事量が多く残業続き
仕事量が多く残業が続く職場は気疲れしやすい環境だといえます。
厚生労働省の「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)」(※2)によると、「仕事・職業生活での強い不安やストレスを感じる労働者」は53.3%と過半数を超えていることが分かりました。そして、「仕事や職業生活に関する強い不安やストレスを感じる」とした労働者の中で、ストレスの原因として最も割合が高かった項目は「仕事の量(全体の43.2%)」です。
このことから、仕事量が多い職場では多くの人がストレスを感じやすいと考えられます。業務時間が増えることにより、自宅でリフレッシュする時間が設けられず、気疲れにつながるケースもあるでしょう。
関連記事:働く大人のメンタルヘルス不調の原因と症状について【専門家監修】
関連記事:仕事でのメンタルヘルス不調のサインは?ストレスを感じたらすべきこと5つを解説
3.3転職や引っ越しなどで環境に大きな変化があった
転職や引っ越しなどで環境に大きな変化が生じた場合、人間関係を一から作り上げなければならないため、気疲れすることが多くあります。慣れない人の中で人間関係を構築する際、強い緊張を感じてしまったり、気を遣う場面が普段より増えたりするためです。
また、仕事のみならず妊娠・出産による環境の変化で精神的に疲れやすくなる方もいます。
4.気疲れの解消法 | 内面・環境それぞれへの対処法
ここからは、気疲れの解消法を内面・環境それぞれに分けて紹介します。気疲れの原因に適切にアプローチし、原因を取り除くように心がけましょう。
4.1内面への対処
まずは、内面への対処法を紹介します。
気疲れは、もともとの性格や考え方のクセから生じていることも多くあります。セルフケアを取り入れて精神を安定させ、考え方を少しずつ変えることで、気疲れの根本的な原因をなくしていきましょう。
4.1.1深呼吸などのリラクセーション法を取り入れる
気疲れの内面への対処として、深呼吸などのリラクセーション法を取り入れることは有効です。
気疲れしやすい人はストレスを感じる場面が多くあるため、呼吸が浅くなっていることもあります。深呼吸すれば、不安や憂うつなどのネガティブな気持ちを和らげられたり、頭がすっきりしたりします。
こころと身体は密接につながっているため、人間関係で過度に疲れてしまう人はまず深呼吸によって身体をリラックスさせましょう。
4.1.2自身の気持ちを大切にする
気疲れしやすい人は、自身の気持ちに耳を傾けるようにしてみましょう。
「過度に人目を気にすること」や「必要以上に責任感を感じてしまうこと」などは、自身よりも他者や組織を優先している状態です。気疲れの原因になるため、自身の気持ちに耳を傾けて、行動を少しずつ変えていくことが大切です。
例えば、以下のような行動を心がけることで自分自身の気持ちを優先できる場面が増えてきます。
- 友人とご飯を食べに行く際、友人の意見を優先するのではなく自分が行きたい店を提案してみる
- 苦手な人と無理に関わるのをやめる
思考や行動のすべてをいきなり変えることは困難ですが、比較的ハードルの低い改善法を少しずつ行ってみましょう。
4.2環境への対処
気疲れを減らすためには、外部に働きかけるなどして環境へ対処することも重要です。ここでは、環境への対処を2つ紹介します。
4.2.1仕事への取り組み方を変える
仕事への取り組み方が気疲れの原因になっているケースはよくあります。
仕事量が多い場合、業務効率化を図ることが重要です。気疲れしやすい人は、責任感が強く仕事を完璧にこなそうとするため、普通の人以上に仕事で疲労を感じてしまうケースが多くあります。
過度なチェックを減らす、疲れている時は無理をせずに休憩するなどして、仕事への取り組み方を変えてみましょう。
また、あまりにも業務量が多い場合、思い切って上司に掛け合ってみることも検討してください。
4.2.2性格が合わない人との交流を減らす
気疲れしてしまう場合、性格が合わない人との深い交流を避けることも有効です。
すべての人と人間関係をうまく築かなければいけないなどと感じていませんか。しかし、性格には合う・合わないがあるため、すべての人間と良好な人間関係を築くことは困難です。
性格が合わない場合、ご飯を食べに行くなどの交流を避け、あいさつなどの簡単なコミュニケーションにとどめるのも1つの手です。一緒にいて楽だと感じる人とは深い交流をし、合わないと感じる人とは適度な距離感を保つように心がけてみてはいかがでしょうか。
5.気疲れを解消できない場合は専門家に頼ろう
本記事では、気疲れしやすい人の原因や特徴、対処法を紹介しました。
気疲れしやすい理由としては、完璧主義や過度に人目を気にしてしまうなどの内面の要因、複雑な人間関係の中にいるなどの環境の要因があります。
気疲れしやすい人は、苦手な人と無理に交流するのをやめるなど自身の気持ちに耳を傾けるようにしてみることで、人付き合いが楽になる可能性があります。
また、気疲れを解消できない場合は専門家に頼ることも有効です。「人間関係で過度に疲れてしまう」・「強い不安を感じる」といった場合、他者との交流に強い不安・恐怖を感じる社交不安障害などのこころの病が隠れている場合もあります。対人関係での悩みが強い場合は無理をせず、専門家に相談してみましょう。
<編集部より>
「誰かに悩みを聴いてもらいたい…」そんなとき、臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、シニア産業カウンセラーなどの専門資格を持つ心理カウンセラーに相談できる『メンタルヘルス カウンセリングサービス』をご存じですか?詳しくはこちらをご覧ください。
***************
≪執筆者プロフィール≫
Webライター・藤田サキ
大学では心理学を専攻。教育やキャリアなど幅広い分野の心理学を学ぶ。
***************
参考
- (※1)【出典】政府統計の総合窓口(e-Stat)「国民生活基礎調査 令和4年国民生活基礎調査 健康」https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450061&tstat=000001206248&cycle=7&tclass1=000001206254&stat_infid=000040071885&tclass2val=0
- (※2)【出典】厚生労働省「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況 【個人調査】」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r03-46-50_kekka-gaiyo02.pdf
- 厚生労働省e-ヘルスネット「妊娠・出産に伴ううつ病の症状と治療」 東京大学大学院医学系研究科 精神保健学分野 教授 ⻄ ⼤輔
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-001.html
※当記事は、2023年7月に作成されたものです。
※医師の診断や治療法については、各々の疾患・症状やその時の最新の治療法によって異なります。当記事がすべてのケースにおいて当てはまるわけではありません。



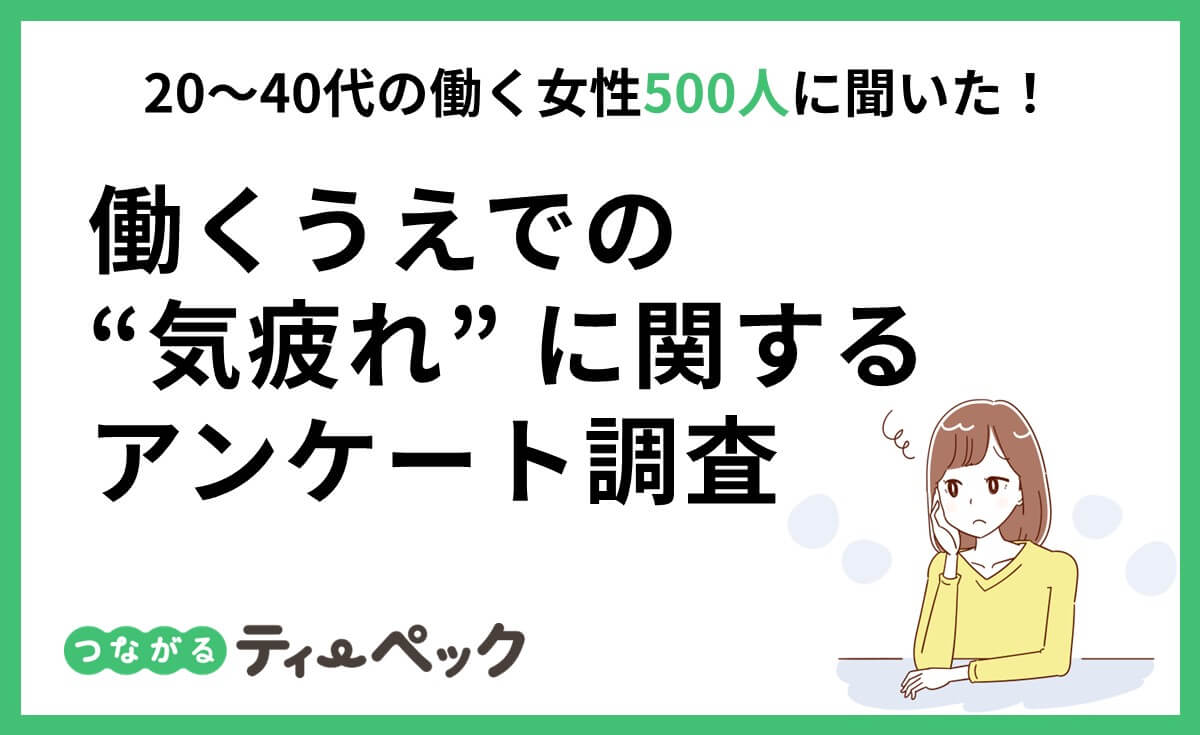


いただいたコメントはつながるティーペック事務局に送信されます。 サイトに公開はされません。 コメントには返信できませんのでご了承ください。